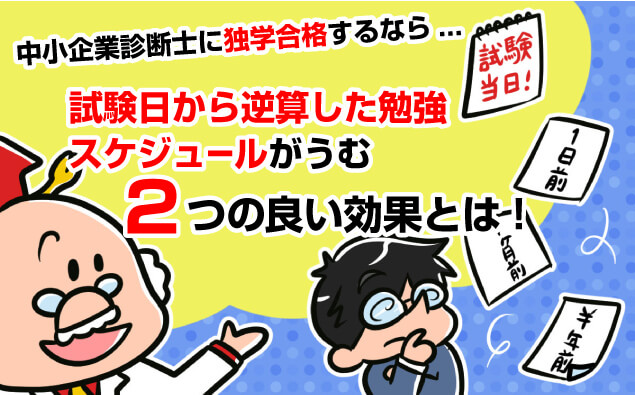関連記事

面倒くさそうだけど...
1日のタスクを紙に書くと、やることを忘れないのと一緒で中小企業診断士の勉強でも大事なんだな。

中小企業診断士の試験日から逆算して勉強スケジュールをたてることによって、進捗管理の徹底、不安や心配などの邪念を取りのぞけるので勉強に集中できる、合格点をとるためにバランスの良い勉強配分と3つの良い効果がうまれます。
そして、
- 月・日別単位でスケジュールを細分化する
- インプット期・アウトプット期・直前期の3期に分ける
が逆算した勉強計画をたてるコツです。
試験日から逆算した勉強スケジュールが中小企業診断士の独学合格に必要な2つの理由
![[理由は2つ]試験日から逆算した勉強スケジュール・計画が中小企業診断士の独学合格に必要[中小企業診断士アール博士の合格ラボ]](https://kokushi11.com/jsmeca/wp-content/uploads/2019/11/jsmeca-schedule-sikennbi-gyakusann-dokugakugoukaku.png)


進捗管理が重要なのは試験だけじゃない
上司への新規事業の企画書を30日後に提案が必要な場合、納得してもらえる内容を作るには、上司が求める方向性の確認、顧客が求めるニーズ調査、会社が持っているリソースを使った実現方法、収支予測などの工程を踏んでいきます。
滞りなく30日後までにキッチリと完成させるには、遅れがでていないか、遅れがでている原因と対策によるリカバリーの実施、をするために進捗管理が必要となります。
同じように、中小企業診断士に合格には期限である試験日から逆算したスケジュールで勉強計画をたてる1番大きな目的は
- 進捗管理の徹底
です。
しかも、朗報なのが勉強計画をたてることは、進捗管理以外に2つの波及効果を及ぼすため、一石三鳥のおトクな作業だと断言できます。
逆算した勉強計画がもたらす効果
- 不安や心配などの邪念を取りのぞけるので勉強に集中できる
- 合格点をとるためにバランスの良い勉強配分が可能
[ムダな労力の排除]不安や心配などの邪念を取りのぞけるので勉強に集中できる

勉強スケジュール・計画をたてると勉強のゴールがはっきりやるべきことだけに集中できるから結果として実力が身につきやすいんだな。

中小企業診断士の試験科目は一次試験で7科目、二次試験4科目の全11科目あります。
勉強範囲が広いため、各科目で学習すべき内容は出題される可能性の高い論点から優先順位をつけた勉強をすべきです。
しかし、勉強スケジュールをたてないと行き当たりばったりとなるため、実力がついているか不安になってしまいます。
過去問を解いた時にテキストに載っていない内容があると気になって、他のテキストや問題集を色々とつまみ食いしてしまう行為はその典型例です。
勉強スケジュールを立てればゴールを見据えた行動ができるため、現在地を確認しながら自信を持って勉強に望めます。
つまり、勉強計画をたてると何をやらないのか決める事となるため、
- ムダな労力を削減
につながります。
ポイント
- 中小企業診断士の試験科目はとても多いため各科目の勉強範囲を広げるべきはでない
- しかし、勉強スケジュール・計画を立てないとゴールが分からず色々とつまみ食いして勉強範囲を広げてしまう可能性が高い
- 勉強スケジュール・計画を立てれば、ゴールもやるべき事もはっきりしているので、決めた勉強範囲だけを自信持って勉強できる
[不得意科目をつくらない]合格点をとるためにバランスの良い勉強配分が可能

あと、もう1つの効果は何だろう?
つまり、不得意科目をつくらない戦略をとれることなんだな。

中小企業診断士の一次試験の合格率は例年20%ほどとであるものの、各科目の合格率は年度によって大きく異なります。
これは、科目合格制度によって科目ごとで受験者数がバラバラな中で、一次試験全体の合格率を20%ほどになるよう調整する結果、年度によって合格率を大きく変動しているものと推測されます。
科目ごとの難易度が年度によって大きくバラツキがでる以上、不得意科目をつくらずどの科目であっても安定して合格点をとる勉強法を取ることが重要です。
勉強スケジュール・計画をたてると進捗管理ができるので、どこが理解できていないか、科目ごとに勉強配分の偏りがないかが一目瞭然となります。
結果として
- 勉強配分の最適化が不得意科目をつくらない勉強戦略
につながります。
ポイント
- 不得意科目をつくらず、どの科目であっても安定して合格点をとること
- 勉強スケジュール・計画は進捗管理をすることと一緒
- すると、弱点科目を作らないために勉強配分の最適な化が可能
試験日をまず確認!中小企業診断士に独学合格するための勉強スケジュールを立てるコツ
![試験日をまず確認!中小企業診断士に独学合格するための勉強スケジュールを立てるコツ[中小企業診断士アール博士の合格ラボ]](https://kokushi11.com/jsmeca/wp-content/uploads/2019/11/jsmeca-schedule-sikennbi-kotu.png)
まずは両方の試験日を確認してみるんだな。

2024年中小企業診断士一次試験の試験スケジュール
|
時期 |
内容 |
|
4月25日(木)~5月29日(木) |
受験申込受付期間 |
|
8月3日(土)・4日(日) |
試験日(2日間) |
|
9月3日(火) |
1次試験合格発表 |
参照中小企業診断士診断協会(令和5年度日程試験について)
中小企業診断士の一次試験スケジュールで見るべきは、試験日の8月5日・6日です。

2024年中小企業診断士二次試験の試験スケジュール
|
時期 |
内容 |
|
8月23日(金)〜9月17日(火) |
受験申込受付期間 |
|
10月27日(日) |
二次筆記試験 |
|
1月15日(水) |
口述試験を受ける方の発表日 |
|
1月26日(日) |
二次口述試験 |
|
2月5日(水) |
二次口述試験合格発表 |
参照中小企業診断協会(令和6年度日程試験について)
二次試験スケジュールも一次試験と同じで、試験日の10月27日を軸に勉強計画を逆算することが重要です。

-

-
中小企業診断士の試験内容とは?試験日、科目免除などを解説
関連記事 中小企業診断士の難易度 独勉クン中小企業診断士の試験内容ってどうなっているんだろうか... 試験概要(試験日・受験料、受験資格)と試験科目、科目免除・科目合格制度の3つを知れば中小企業診断士 ...
続きを見る
中小企業診断士の独学合格に必要な目安勉強時間から勉強スケジュールを立てるのが鉄則


中小企業診断士の合格目安は1,000時間なんだな。


中小企業診断士の目安時間は1,000時間と言われています。
ただ、独学だと1.2〜1.5倍ほど余分にかかるのが一般的なので、独学で合格を目指すなら1,200〜1,500時間必要となります。
メモ
- 中小企業診断士の目安勉強時間は1,000時間で、独学なら1,200〜1,500時間ほど
- 一次試験の科目別勉強時間も把握しておくこと
- 二次試験の科目別勉強時間も同様
中小企業診断士の試験日と目安勉強時間から逆算した勉強スケジュールの具体的な立て方


だけど、何すればよいのか全然思いつかない...
綿密なものをたてる必要はないからめんどくさがる必要もないんだな。


中小企業診断士の試験日と勉強時間が把握できたら、あとは逆算した勉強スケジュール・計画をたてることができれば完成です。
逆算した勉強スケジュール・計画といっても、大したことをするわけではなく3つの期に分けて進捗管理をすることで、勉強時間の最適配分を常に行うだけです。
勉強開始日から一次試験の試験日の8月上旬(2020年度は7月中旬)から残り月別or日数と700時間、独学なら840〜1,050時間で割って月別や日別でを割り出すと具体的にイメージしやすくなります。
11月からの独学で開始であれば、1,200〜1,500時間÷7.5ヶ月=160〜200時間(月)、日別に直すと、5.3〜6.6時間が1日平均で必要といった具合です。


あとは、時間をどこで確保するかを自分なりに考えればよさそうだ。
逆算スケジュールは3つの期に分ける
- インプット期
- アウトプット期
- 直前期
中小企業診断士の勉強スケジュール最初はインプット期(9〜12or1月)


メモ
- インプット期の勉強は各科目の基本事項の徹底理解に努めること
- 科目別学習段階であり、点数がとれなくても問題ないため、知識の定着を課題にすべき
- テキストで学習した内容を過去問ですぐに実践してどのように問われるのか把握すること
- 科目数が多いので、終わった科目も1日5分だけでも復習しておくと知識の定着度が全然ちがう
中小企業診断士の勉強スケジュール中盤はアウトプット期(2〜7月)


インプット期で覚えた学習内容の定着を図るため、過去問の回転数を高めて解くことにつきます。
また、実力を養成するのと同時に苦手科目や苦手分野の把握をし、弱点克服にも力を入れることが重要です。
そこでポイントとなるのが、逆算した勉強計画の進捗管理です。
進捗管理するために
- どの科目のどの論点を何時間勉強したのか、どの論点をよく間違えるのかを日々記録
しておくと、勉強時間の最適な配分が不得意科目をつくらない勉強戦略の実現が可能となります。
ポイント
- 過去問演習していて、何度も何度も間違える問題は理解できていない苦手な論点
- このような論点は知識が定着する前でしつこく繰り返し復習すること
中小企業診断士の勉強スケジュール終盤は直前期(8月)


ポイント
- 各科目の基本事項や頻出論点の再確認をする最終調整の時期
- カゼをひいて試験当日に100%の力を出せないと1年の勉強を棒に振ることになる
- だから、直前期は体調にも気を使うべき
まとめ
![まとめ[中小企業診断士アール博士の合格ラボ]](https://kokushi11.com/jsmeca/wp-content/uploads/2019/11/matome2.jpeg)
![まとめ[中小企業診断士アール博士の合格ラボ]](/jsmeca/wp-content/uploads/2019/11/matome2.jpeg)
中小企業診断士の試験日から逆算して勉強スケジュール・計画をたてることは
- 進捗管理の徹底
- 不安や心配などの邪念を取りのぞけるので勉強に集中できる
- 合格点をとるためにバランスの良い勉強時間の配分が可能
とメリットしかありません。
試験日から逆算した勉強スケジュール・計画をしっかりとたてて、効率のよい勉強を行いましょう。