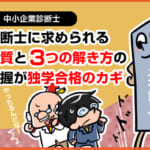関連記事

分かってはいるけど、なかなか得点がとれない...
ライバルと一歩差をつけるためには得点がとれていない原因が何かを解明することが勉強法のコツなんだな。

中小企業診断士の二次試験(事例4)財務会計で思うような得点がとれずに不合格となる人がいる一方で、 高得点を獲得できたことで、他科目をカバーして合格する人も存在します。
事例4(財務会計)で高得点が取れる人の共通項は
- 計算力
- 記述力
の2つのパートに分けて勉強をしていることです。
中小企業診断士の二次試験(事例4)財務会計で60点を安定的にとるための勉強方法は至ってシンプルで、誰でも実践できる内容となっています。
[事例4:財務会計]中小企業診断士二次試験の概要
![[事例4:財務会計]中小企業診断士二次試験の概要[中小企業診断士アール博士の合格ラボ]](https://kokushi11.com/jsmeca/wp-content/uploads/2020/02/jirei4-gaiyo.png)


試験概要は3つ
- 試験時間
- 試験形式
- 出題範囲
試験時間
80分
試験形式
論述形式
ポイント
- 財務・会計の視点から企業の経営課題を解決する助言・アドバイスが求められる
出題範囲
経営戦略および財務・会計における診断・助言
ポイント
- 財務会計は二次試験の中で唯一、計算問題が存在する
- 正式な解答が公表されない中で、計算問題だけは確実に得点をとる拠りどころ
- しかし、計算問題ができても記述問題ができず不合格になるケースも存在するため、計算問題以上に記述問題が大切
事例4(財務会計)の中小企業診断士二次試験における勉強方法(解き方)
![事例4(財務会計)の中小企業診断士二次試験における勉強方法(解き方)[中小企業診断士アール博士の合格ラボ]]](https://kokushi11.com/jsmeca/wp-content/uploads/2020/02/jirei4stduymethod-rdoctor.png)

記述問題をどのように対応すればいいのか心配だ...

中小企業診断士二次試験の事例4(財務会計)で重要な勉強方法は
- 計算力
- 記述力
の2つを高めることにつきます。
事例4(財務会計)は、計算問題がメインのようにうつりがちですが、事例1、事例2、事例3と本質は一緒です。
得点をとるためには、計算問題よりも経営課題の解決策を提示し企業が成長するストーリーに従った解答の記述が絶対的な重要事項であることを忘れてはなりません。
-

-
中小企業診断士二次試験の解き方とは?独学で合格するなら診断士に求められる本質と3つの解き方の把握が攻略のカギ
関連記事 中小企業診断士の独学合格ノウハウ 独勉クン中小企業診断士二次試験ってどんな解き方をすればいいのかな... どんな風に勉強すれば良いかわからず、手探り状態だ... 二次試験に独学合格を目指すの ...
続きを見る
計算力を高めたいなら計算過程の見える化をすべし


計算問題って具体的にどんな風に解いていくんだろう...
だからこそ、計算過程の見える化をすることが重要なんだな。


事例4の計算力を高めるためには、計算過程の見える化する力をみにつけることにつきます。
朝から緊張状態の中かつ、事例1〜3の問題を頭フル回転させて解いた最後に計算問題の事例4(財務会計)だと、普段の勉強ではありえないようなうっかりミスや計算ミスが発生しがちです。
計算問題を頭で考えるのではなく作業としてこなすために、手順化・マニュアル化のツールとして計算過程の見える化を活用することでミスは大幅に減らせます。
さらに、計算過程の見える化の練習によって、公式に数字を当てはめるだけの丸暗記対応ではなく、公式の根拠を深く理解できるため、現場対応力の向上にも繋がります。
とは言うものの、自力での事例4の強化に不安を感じるなら、計算過程の見える化をベースに事例4の解き方や考え方を教えてくれる弥生カレッジCMCの講座受講が最適です。
平成30年までの内容ではありますが、14,080円で安価で購入可能なのでお財布にも優しい講座となっています。
計算の見える化で事例4を強化
ポイント
- 事例4で合格点をとりたいなら計算過程の見える化が重要
- 手順化・マニュアル化のツールとして使えるためミスを大幅に減らせる
- 公式の根拠を深く理解できるため、現場対応力が向上する
2018年度(平成30年度)第3問設問1:損益分岐点分析(CVP分析)を例に解説


でも、どうやって計算過程の見える化をすればいんだろう...


損益分岐点分析(CVP分析)
損益分岐点分析とは、利益ゼロのトントンになる売上高はいくらか把握するための計算
- 費用は、変動費(売上高や売上数量によって増減する費用)と固定費(どれだけ使っても一定額かかる費用)に分別する
- 限界利益(限界利益 = 売上高 − 変動費 or 固定費 + 利益)とは、営業利益が赤字であっても限界利益が+であれば固定費は回収できているため、関連事業の強みの源泉になっている場合は、事業は継続するといった判断指標に使うもの
- なお、通常は営業利益ベースで算出するが、経常利益ベースで算出する場合は営業外費用と営業外収益は固定費に加減算する
見える化のポイント
- 売上高 = 変動費 + 固定費 + 利益の損益計算書を作ること
設問の予測損益計算書をもとにCVP分析を行うことによって、以下の金額を求め、 a欄にその金額を、b欄に計算過程を、それぞれ記入せよ。
第X2期の損益計算書は、売上が2,150百万円、売上原価1,770百万円のうち固定費が1,020百万円、販管費320百万円のうち固定費が120百万円だった。
なお、解答にあたっては、金額単位を百万円とし、百万円未満を四捨五入すること。
第×3期において100百万円の経常利益を達成するために必要となる売上高はいくらか。
参照2018年度(平成30年度)第3問設問1(ア)一部改編


|
項目 |
X2期 |
X3期 |
|
売上 |
2,150 |
X |
|
変動費 |
950 |
950/2,150 X |
|
限界利益 |
1,200 |
X ー 950/2,150 X |
|
固定費 |
1,151 |
1,151 |
|
経常利益 |
49 |
100 |
見える化作業の5ステップ
- 設問から固定費と経常利益のマスを埋める
- 売上を求めるため、Xとおく
- 変動費は売上に比例する費用であるため、X2期の950/2150(変動比率)に第X3期の売上であるXをかける
- X(売上) = 950/2150 X(変動費) + 1,150(固定費) + 100(利益)
- これを計算すると、2,241百万円となる


[重点学習すべきポイント]中小企業診断士二次試験の財務会計の頻出論点
![[重点学習すべきポイント]中小企業診断士二次試験の財務会計の頻出論点[中小企業診断士アール博士の合格ラボ]](https://kokushi11.com/jsmeca/wp-content/uploads/2020/02/jirei4-kowledge.png)
![[重点学習すべきポイント]中小企業診断士二次試験の財務会計の頻出論点[中小企業診断士アール博士の合格ラボ]](/jsmeca/wp-content/uploads/2020/02/jirei4-kowledge.png)


よく出題される論点から優先して勉強することで、効率よく力をつけたいな...
事例4(財務会計)の頻出論点は5つなんだな。


代表的な5つの頻出論点
- 経営分析
- 損益分岐点分析(CVP分析)
- キャッシュフロー計算(CF計算)
- 設備投資の経済性計算
- 企業価値
経営分析




経営分析は、損益計算書と貸借対照表から会社の状態を分析する指標です。
健康診断と一緒で会社の状況を知るための分析であるため、毎年必ず第1問で出題される最重要な頻出論点となっています。
|
年度 |
配点 |
|
2019年度(令和元年度) |
24点 |
|
2018年度(平成30年度) |
25点 |
|
2017年度(平成29年度) |
25点 |
|
2016年度(平成28年度) |
25点 |
|
2015年度(平成27年度) |
28点 |
過去10年の最低配点が24点と、とても高いため必ず得点しなければならない論点で
- 収益性
- 効率性
- 安全性
の3つの観点から記述が求められます。
指標選択のポイント
- 粗利益率の数値が悪い:売上原価の高さを疑う
- 営業利益の数値が悪い:販管費の高さを疑う
- 経常利益率の数値が悪い:営業外費用(借入れ)の高さを疑う
損益分岐点分析(CVP分析)


得意な論点に仕上げるぞ〜
ほぼ毎年出題されていて、比較的とりやすい問題なことが多いんだな。


損益分岐点分析(CVP分析)は、予想損益計算書の作成とセットで出されるパターンが多いです。
先ほどの2018年度(平成30年度)過去問題のように表をつくり、マスを埋めていきさえすれば確実に得点できる論点です。
|
年度 |
配点 |
|
2019年度(令和元年度) |
24点 |
|
2018年度(平成30年度) |
25点 |
|
2017年度(平成29年度) |
25点 |
|
2016年度(平成28年度) |
25点 |
|
2015年度(平成27年度) |
28点 |
記述問題では
- 売上高
- 変動費
- 固定費
のうち、どのポイントが大きく影響を及ぼしているのか、与件文の具体的内容とあわせて問われます。
ポイント
- 予想損益計算書とセットのパターンが多い
- 計算過程の見える化さえできれば、マスを埋めるだけなので得点をとりやすい論点
- 記述は、売上高、変動費、固定費のうち何が大きく影響しているかの分析問題が多い
キャッシュフロー計算(CF計算)


実務補習でもキャッシュフローをベースにした提案することがあるから学んで損はないんだな。


中小企業診断士の二次試験事例4(財務会計)でキャッシュフローはとても重要な論点です。
資金繰りの現状把握はもちろん、設備投資の経済性計算や企業価値などを算出するベースとしても使われるため、キャッシュフローの算出ができないと、事例4(財務会計)で大きく得点することは不可能となります。
キャッシュフローを算出する方法は全然難しくなく、損益分岐点分析(CVP)分析同様に、表をつくってマス目に埋めていきさえすれば得点は取れるようになっています。
|
項目 |
金額 |
|
売上 |
|
|
売上原価 |
|
|
販管費 |
|
|
営業利益 |
|
|
営業外損益 |
|
|
経常利益 |
|
|
法人税 |
設問分や与件文から損益計算書を作成したのちに、キャッシュフロー計算のポイントとなる
- 営業外損益
- 原価償却費
- 法人税等
の3つを加減算し、営業活動CFを算出します。
|
項目 |
金額 |
|
経常利益 |
|
|
営業外損益(除却損など) |
|
|
減価償却費 |
|
|
法人税等 |
|
|
営業CF合計 |
キャッシュフロー(CF)計算は営業利益ベース(事業活動に対して自由に使えるお金)であるため、経常利益を起点に計算することが重要です。
営業外損益(除却損など)や減価償却費は、費用ではあるものの実際にキャッシュ(現金)の支払いなどが発生していないため、費用ではあるものの、キャッシュフロー計算(CF計算)では損益計算書から足し戻すこととなります。
ポイント
- 損益計算書ができれば、キャッシュフロー計算書は必ず作成できる
- 減価償却や営業外収益(除却損)など、損益計算書上では費用や収益であるが、実際にはキャッシュ(現金)の支払いなどが発生していないものは、キャッシュフロー計算書上では足しもどす
過去問でチェック
機械設備gは、取得原価50百万円、年間減価償却費10百万円、残存耐用年数年である。なお、利益に対する税率は30%とする。
増加する各期のキャッシュ・フロー(当初投資時点の投資額を含まない)を計算せよ。
第X3期
第X4期
第X5期
売上(現金収入)
100
250
250
費用(現金支出)
70
150
150
投資額
5
単位:万円
参照平成27年度中小企業診断士事例4第3問設問1を改編


まずは損益計算書を作成すしていくから...
|
第X3期 |
第X4期 |
第X5期 |
|
|
売上(現金収入) |
100 |
100 |
100 |
|
支出(現金支出) |
70 |
70 |
70 |
|
減価償却費 |
10 |
10 |
10 |
|
経常利益 |
20 |
20 |
20 |
|
法人税等 |
6 |
6 |
6 |


|
第X3期 |
第X4期 |
第X5期 |
|
|
経常利益 |
20 |
20 |
20 |
|
減価償却費 |
10 |
10 |
10 |
|
法人税等 |
▲6 |
▲6 |
▲6 |
|
営業活動CF |
24 |
24 |
24 |
|
投資活動CF |
▲5 |
||
|
CF合計 |
19 |
24 |
24 |
ポイント
- キャッシュフロー計算は、設備投資の経済性計算や企業価値を算出するベース
- 計算自体は難しくなく、損益計算書の作成と経常利益をベースに減価償却費などのキャッシュアウトしない費用を表に入れれば完成する
設備投資の経済性計算


何をどうしたよいのか分からない...


設備投資の経済性計算は、プラスであれば投資すべき・マイナスであれば投資すべきでないと設備投資の可否を判断するために使われる指標です。
ただし、計算自体はなんら難しくなく、キャッシュフロー計算さえできていれば、後は投資額を引けばよいだけです。
ポイント
- 設備投資は現時点で行うため、将来発生するキャッシュフローを現在価値に割り引くことを求められる場合もある
過去問でチェック
機械設備gは、取得原価50百万円、年間減価償却費10百万円、残存耐用年数年である。なお、利益に対する税率は30%とする。
増加する各期のキャッシュ・フロー(当初投資時点の投資額を含む)を計算せよ。
投資時点
第X3期
第X4期
第X5期
売上(現金収入)
100
250
250
費用(現金支出)
70
150
150
投資額
20
5
単位:万円
参照平成27年度中小企業診断士事例4第3問設問1を改編


あとは投資時点の20百万円を引けばいいってことか...
金額がプラスだから投資すべきとの判断ができるんだな。


まとめ
![まとめ[中小企業診断士アール博士の合格ラボ]](https://kokushi11.com/jsmeca/wp-content/uploads/2019/11/matome2.jpeg)
![まとめ[中小企業診断士アール博士の合格ラボ]](/jsmeca/wp-content/uploads/2019/11/matome2.jpeg)
計算力と記述力を高められればよいんだな。


事例4(財務会計)は、中小企業診断士二次試験の解答がブラックボックスにおいて、唯一正解が確実にわかる事例です。
計算問題を得点できれば高得点をとれる可能性が増加し、ひいては二次試験の合格確率を高めます。
そのためには計算問題を頭で考えるのではなく作業としてこなすために、手順化・マニュアル化のツールとして計算過程の見える化を活用することで、計算ミスをいかに減らすかにつきます。


記述力は事例共通だから、二次試験の解き方をしっかり学ばないとな...
-


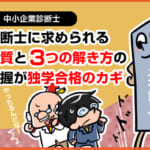
-
中小企業診断士二次試験の解き方とは?独学で合格するなら診断士に求められる本質と3つの解き方の把握が攻略のカギ
関連記事 中小企業診断士の独学合格ノウハウ 独勉クン中小企業診断士二次試験ってどんな解き方をすればいいのかな... どんな風に勉強すれば良いかわからず、手探り状態だ... 二次試験に独学合格を目指すの ...
続きを見る

![中小企業診断士の二次試験事例4で60点を死守する勉強法のコツ[アール博士の中小企業診断士合格ラボ]](https://kokushi11.com/jsmeca/wp-content/uploads/2020/02/jirei4.jpg)