
早く合格して立派な中小企業診断士になりたいな...
最終関門として実務補習(実務従事)が待っているんだな。

試験に合格しただけでは中小企業診断士と名乗ることはできません。
中小企業診断士になるには15日間の実務に従事が必要で、そのための場所として、中小企業診断協会が実施する実務補習が存在します。
多額の費用や時間がかかるため、中小企業診断士の取得を目指す前から
- 実務補習の実態
を把握しておいて損なことはありません。
さらに、あまり知られていませんが、実務補習以外の裏ルートの存在も判明しました。
中小企業診断士の実務補習における日程と費用
![中小企業診断士の実務補習における日程と費用[中小企業診断士アール博士の合格ラボ]](https://kokushi11.com/jsmeca/wp-content/uploads/2020/04/jsmeca-jitsumuhosyu-dayandprice.png)

実務補習を受けて晴れた有資格者として名乗れるんだけど、意外とハードでお金はかかるんだな...

実務補習で知るべき2つ
- 日程
- 費用
日程

15日コースを例にあげたけど、1社5日間×3社と、かなりみっちりな日程なことがわかるはずなんだな。

8〜10月(5日間コースのみ)、2〜3月の大きく2クールの期間に実務補習は例年実施されます。
エリアによっては開催時期が異なるため、注意が必要です。
実施地区
東京・札幌・仙台・大阪・広島・福岡
|
実施日(15日コース) |
|
2/3(金),4(土),11(土),12(日),13(月),17(金),18(土),25(土),26(日),27(月) 3/3(金),4(土),11(土),12(日),13(月) |
実施地区
名古屋
|
実施日(15日コース) |
|
2/2(木),3(金),11(土),12(日),13(月),16(木),17(金),25(土),26(日),27(月) 3/3(金),4(土),11(土),12(日),13(月) |
ポイント
- 札幌、福岡地区以外は定員あり
- 東京、大阪は例年すぐに定員に達するため、早めの申し込みが吉
費用

費用はどのくらいかかるんだろう...
人によっては、ノートパソコンや交通費代などの費用もかかるから、かなりの出費になるんだな。

|
15日間コース |
5日間コース |
|
180,000円(テキスト代込) |
60,000円(テキスト代込) |
ポイント
- 実務補習を受けると、15日間合計で15万ほど費用がかかる
- ノートパソコンは必須となるので、持っていない方は購入する必要あり
- さらに、交通費やメンバー同士や指導員の先生を交えた懇親会費もかかる
- トータルで20〜30万ほどかかると考えておくべき
実務補習でとりくむ内容は中小企業診断士の基礎スキル
![実務補習でとりくむ内容は中小企業診断士の基礎スキル[中小企業診断士アール博士の合格ラボ]](https://kokushi11.com/jsmeca/wp-content/uploads/2020/04/jsmeca-jitsumuhosyu-basicskill.png)

具体的には事前準備、ヒアリング、SWOT分析等、担当別に報告書作成、プレゼンの5つに分けられるんだな。

実務補習では、1クール(5日間)で1社の経営診断報告書を作成します。
経営診断報告書には経営課題や解決施策の提案をすることが求められます。
実務補習で、担当する業種・企業は、基本的に担当する指導員と関連のある企業となるため、製造業、サービス業、運用業、商店街などなど様々です。
|
内容 |
開始前 |
1日目 |
2日目 |
インターバル |
3日目 |
4日目 |
5日目 |
|
準備 |
arrow_forward | ||||||
|
ヒアリング |
arrow_forward | ||||||
|
SWOT分析等 |
arrow_forward | ||||||
|
報告書作成 |
arrow_forward | arrow_forward | arrow_forward | ||||
|
プレゼン |
arrow_forward |
注意指導員や企業の事情により必ずしも上記の通りになるとは限りません
開始前:事前準備

何か調べ物をしたりするのかな...?
実務補習初日の直前に担当の指導員から事前準備に関する連絡がくることがほとんどなんだな。

ポイント
- 実務補習実施日の4~5日前になると、担当の指導員からメールが送られてくる
- そこで診断先の企業情報や当日までの準備事項の通達がある
- 必ず診断先の情報収集と業界分析は必ず行っておくべき
- 業界の分析には業種別審査辞典が便利(大きな図書館では取り扱いがある)
1日目:ヒアリング

初日からヒアリングとは緊張しそう...
ヒアリングの良し悪しで、報告書の質が決まると言えるほど重要なパートなんだな。

ポイント
- 初日に企業訪問しヒアリングを実施するため、訪問時間によっては打合せもほとんどない
- だからこそ、ヒアリング内容の整理や担当分けは事前にメンバー間で行っておくべき
- 別日に追加ヒアリングを実施してくれる場合もあるが、社長や社員に話を聞けるのは原則一回限り
- ヒアリングの巧拙で報告書の出来は大きく左右されるため、準備をしっかしておくべき
2日目:SWOT分析、経営課題(テーマ)の設定

それってどういうことなんだろう...
チーム全員で合意した上でテーマ設定しないと、担当パートの内容の方向性がバラバラになってしまうから、気をつける必要があるんだな。

2日目はヒアリング結果や事前の調査に基づいて、SWOT分析や必要に応じてその他の分析(VRIO分析、PEST分析等)・調査を行い、実習先の企業の経営課題を抽出し、報告書全体のテーマを設定します。
診断先企業が成長・発展するための阻害要因は何なのか、あるべき姿から逆算した時にどんなことを解決しないといけないのかなど、報告書を作成する上でテーマ(ゴール設定)を決めることです。
報告書全体のテーマを全員で合意した上で決めた上で、個別作業に入らないと一貫性を保つことができず、最終的に何を提案したいのかわからない、価値のない報告書が出来上がってしまいう可能性が高くなります。
だからこそ、ヒアリングでは細かい部分だけでなく、企業としての目標やあるべき姿など社長や従業員がどんな思いをもっているのかも明確に聞いておくべきです。
ポイント
- チーム内の意見が割れてしまうと診断報告書の方向性が定まらない
- 避けるためにはヒアリングによって、どこまで核心部分をひきだせるか
担当パート決めも行う
その時々で担当パートの内容はかわるけど、経営戦略、営業、組織・人事、生産、財務の4パートがベースとなるんだな。

ポイント
- 経営戦略担当者が班長になることがほとんど
- チーム人数が5人以下だと1人で2パート受け持つこともあり、かなりハード
- ベースの4パート以外にも、システム・設備や新事業など業種や企業の状況によって各パートの増減がある
インターバル・3・4日目:担当別に報告書を作成

この期間で報告書をどれだけ進められるかが鍵となるなんだな。

インターバル期間
- 個人作業の期間
- 担当パートごとに課題の整理と改善策の検討を行い、報告書にまとめる
- ページ数は各パート10~20ページほど
- 指導員の先生によっては途中で中間報告を求められる場合もある
3日目:報告書作成

あと、担当指導員のチェックも入るから場合によってはゼロベースに戻ることもあったりするんだな...

ポイント
- 各自作成した診断報告書のチェックとすり合わせ
- 全体の方向性からずれていないか、各パートで矛盾した内容になっていないかなどを確認
- 担当指導員のチェックも入るため、内容が悪いと全てやり直しになる可能性もある
4日目:報告書作成とまとめ作業
5日目の朝に中小企業診断協会に提出するから、4日目までには製本作業は必ず入る必要があるんだな。

ポイント
- 担当パート別に作成した診断報告書を1つにマージ(合体)する作業にも以外と時間がかかる
- 遅くとも15時頃にはマージ作業に入らないと、印刷が間に合わなくなる可能性大
- マージ作業が完了して報告書が出来上がると、キンコーズ等に持ち込んで製本
5日目:プレゼン
ただ、全体で1時間程度なので話すべき内容を簡潔にまとめておくべきなんだな。

ポイント
- 担当パートごとに全員がプレゼンする
- 全体で1時間程度
- 報告書を使う場合と、報告書とは別にパワーポイントを作って臨むこともある
中小企業診断士の実務補習はサラリーマンではきついがなんとかなる
![中小企業診断士の実務補習はサラリーマンではきついがなんとかなる[中小企業診断士アール博士の合格ラボ]](https://kokushi11.com/jsmeca/wp-content/uploads/2020/01/jsmeca-jitsumuhosyu-officeworker.png)

サラリーマンで診断報告書作成、プレゼンまでできるのだろうか...
5日間コースであれば、負荷はかかるけど乗り切れないほどのスケジュール感でもないから、なんとかなるんだな。

中小企業診断士の実務補習は15日間の全てに参加しないと修了できないため、平日は業務の都合で参加できないから、土日だけ参加するわけにはいきません。
なかなか有休が取れないサラリーマンにとっては参加が難しいのは間違いありませんが、5日間コース×3回を3年以内に従事すればOKです。
ポイント
- 5日間コースであれば、業務の都合をつけての参加であれば、実務補習修了のハードルはかなり低くなる
- 実務補習がキツイのは間違いないが、5日間コースを上手く活用すればサラリーマンでもなんとかなる
担当指導員の先生によっては地獄になることも
こればっかりは、担当指導員が誰になるのかは運だからどうしようもないんだな。
ただ、学ぶことは多くあるはずなんだ。

特にダメ出しもせずスルーな感じの方もいれば、とても厳しく指導される方もいるなど、実務補習の負荷は指導員の先生によって大きく異なります。
厳しい指導員に当たると、個人作業中に中間報告を求められます。
帰宅後しか作業のできないサラリーマンには毎日深夜作業となるため、負担はとても大きくなる可能性もあります。
ポイント
- 最初に決めた方向性を3日目にひっくり返す指導員の方もいる
- そうなると3日目は徹夜作業必至となる
- 指導員の先生次第で地獄にもなりうるのが実務補習なので覚悟しておくべき
中小企業診断士の実務補習を受けたリアルな感想
![中小企業診断士の実務補習を受けたリアルな感想[中小企業診断士アール博士の合格ラボ]](https://kokushi11.com/jsmeca/wp-content/uploads/2020/01/jsmeca-jitsumuhosyu-realimpression.png)

生の声を聞けると参考になるのになぁ...

クラウドワークス(クラウドソーシング)と呼ばれるネットサービスを使って中小企業診断士として独立して活動している人に実務補習の感想を寄稿していただきました。
リアルな声となっているので、参考にしてみてください。
私は15日コースに参加し、実習先の業種は商店街、飲食店、製造業とバラエティに富んでいました。
1クールごとに担当指導員も変わります。
指導員によって指導内容が違うことが間々あることもあり、仕事をしながらの報告書作成はとても大変でした。
特に、3社目の担当指導員の先生が厳しく、細かい点まで修正を求められたので、徹夜することにも・・
大変でしたが、診断士としての基礎をきっちり叩き込んでもらえ、今ではとても良い経験だったと感じています。
また、一緒に苦労した仲間とは、今でも酒を飲み交わす仲となっています。
しかも、独立して中小企業診断士として活動する現在では、当時の指導員の先生から継続的に仕事を頂いています。
実務補習で、仲間・指導員といい関係が築けると、その後の活動に大いに役立つはずです。
口コミ収集先クラウドワークスにて実務補習の体験談を依頼
実務補習は中小企業診断協会以外に実務従事の裏ルートは2つある
![実務補習は中小企業診断協会以外に実務従事の裏ルートは2つある[中小企業診断士アール博士の合格ラボ]](https://kokushi11.com/jsmeca/wp-content/uploads/2020/01/jsmeca-jitsumuhosyu-tyuusyoukigyousinndannkyoukaibackroute.png)

もし、合格して受けることを考えるとネックになりそう...
実務従事なら、コースが様々あるので自分が選びたい時期に受けることが可能なんだな。

実務補習以外にも実務ポイントを15ポイント集めれば、中小企業診断士に登録可能です。
つまり、実務補習は絶対に受けなければいけない訳ではありません。
中小企業診断協会のように、実務補習の期間が限定的ではないため、よりフレキシブルに受講できる点は実務銃を選択する大きなメリットであると言えます。
2つの裏ルート
- 民間
- 知り合い
民間で実務従事する
中小企業診断協会よりも経営課題が明確な場合が多いため、より専門的な診断報告書の作成が求められるんだな。

民間のコンサルティング企業などが実施している実務従事に参加することができます。
民間事業者の一例
メリット

民間実務従事のメリットは実務補習よりも、より実践的な内容で取り組めます。
実務補習は定められた一定のフォーマットに沿って報告書作成が求められるため、どうしても浅く広くになりがちです。
民間の実務従事の場合は、事業承継など一つの経営課題にフォーカスされた状態で実務従事の募集が行われるため、求められる内容が深く、そして濃い取り組みができます。
ポイント
- 中小企業診断士登録後に実施した企業から仕事を依頼される可能性アリ
デメリット

メリットの裏返しでもありますが、実施企業によっては実務補習よりも高いレベルの成果物を求められることもあります。場合によっては負荷は実務補習よりも高くなるかもしれません。
ポイント
- 実務従事のポイントを餌に雑務的な仕事をやらせるだけ民間企業もある
- 実務従事サービスを提供する民間企業の評判や実務従事の内容は必ず調べておくべき
知り合いで実務従事する
この場合だと、費用は無料でできることが多いんだな。

知り合いに中小企業の経営者がいる場合、その人に頼んで実務従事を行い、ポイントをもらうことも可能です。
さらに、所属先の企業から許可をもらえれば、取引先などで実施することも可能です。
メリット
- 中小企業診断協会やコンサルティング企業に支払う受講料が必要ない
- 日程なども個人間で調整すればいいので、自分の都合にあわせられる
デメリット
- 担当指導員はおらず助言してくれる人がいないため、自分のスキルアップにはつながらない
- 中小企業診断士に合格した同期の仲間や担当指導員との関わりがない
まとめ
![まとめ[中小企業診断士アール博士の合格ラボ]](https://kokushi11.com/jsmeca/wp-content/uploads/2019/11/matome2.jpeg)

中小企業診断士試験に合格してはじめの一歩が実務補習です。
15日間で約15万円に加えて、ノートパソコン、交通費を考えると、約20〜30万円の資金がかかるため、合格前から準備はしておくのが吉です。
実務補習中はとてもハードではあるものの、取り組む内容は中小企業診断士における基礎スキルです。
なおかつ合格した同期の仲間と一緒にコンサルティングを行うひと時は、非常に楽しい時間となるはずです。

実務補習を受けられるように、合格目指して勉強するぞ〜。
最短合格勉強法をコツコツ実践あるのみだぁぁ。
-

-
中小企業診断士に最短合格する勉強法!?合格者がこっそりやっている3つの勉強法と裏ワザ
関連記事 中小企業診断士の独学合格ノウハウ 独勉クン中小企業診断士の試験内容は理解できた... だけど、最短合格に必要な勉強法はあるのかな... 中小企業診断士は7科目と多岐にわたるから、勉強法を間違 ...
続きを見る

![中小企業診断士の実務補習は何するの?費用や経験者の感想をくまなく紹介【実務従事という裏ルートの存在も判明】[中小企業診断士アール博士の合格ラボ]](https://kokushi11.com/jsmeca/wp-content/uploads/2020/01/jsmeca-jitumuhosyuu.png)
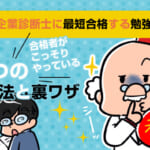
画像(60×60)
15日間コースを受講
30代独立診断士