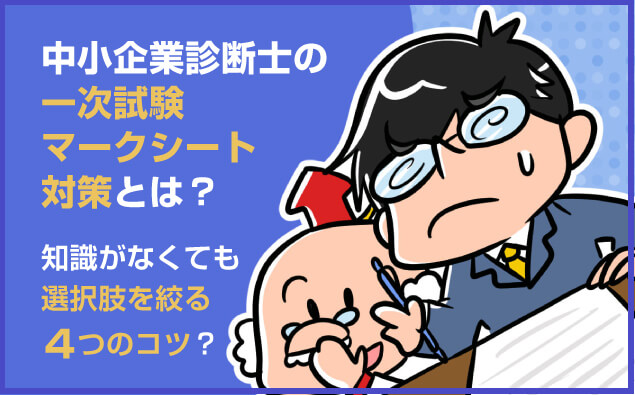関連記事

あ・ん・き、あ・ん・き、あ・ん...
選択肢を絞る(推測する)力を養うのはたった4つのコツを知っているどうかだけだから、ぜひマスターしてほしいんだな。

中小企業診断士の一次試験はマークシート形式なため、間違いなく暗記は必要な学習です。そのため、覚えた内容が字面通りに出題されれば問題ありません。
しかし、やっかいなことに視点を変えた応用問題として形をかえて登場するのが中小企業診断士一次試験の特徴です。
そこで重要となるのが、基礎知識の徹底理解と基礎知識を応用するための推測する(選択肢を絞る)力の2つです。
後者の推測する(選択肢を絞る)力を養うのはとても簡単で
- 選択肢を絞るためのたった4つのコツ
を知り、過去問学習を実践するかどうかだけです。
中小企業診断士の一次試験は完璧な暗記は求められていない
![中小企業診断士の一次試験は完璧な暗記は求められていない[中小企業診断士アール博士の合格ラボ]](https://kokushi11.com/jsmeca/wp-content/uploads/2020/01/jsmeca-itijisikenn-marksheet-annki.png)

むしろ、暗記よりも現場対応力を高めるために本質的な考え方を伸ばす勉強が求められているんだな。

中小企業診断士の一次試験はマークシート形式であるため、暗記に頼ろうと学習をしてしまいがちです。
しかし、一次試験は7科目もあり暗記がそもそも大変な上に、テキストにのっていない知識を問われることも多々あります。
また、テキストにのっていたり、過去問で問われたことがある知識や論点であったとしても角度や見方をかえて出題することがほとんどです。
これは完璧な暗記による対応を前提にした問題設計をしておらず、むしろ基礎的な知識や考え方をベースに経営コンサルタントとして応用力を発揮してほしいとの出題者からのメッセージと受けとれます。
ポイント
- 中小企業診断士は経営コンサルタントの資格であることを意識すべき
- マークシートだからこそ推測する力、考える力が重要
経営コンサルタントの資格であることを意識すべき

だから暗記は大事なんだけど、経営コンサルタント唯一の国家資格として応用力が必要な問題が多いんだな。

ポイント
- 経営コンサルタントは、経営の雑学知識ではなく戦局に一番適したアドバイスが求められる
- その唯一の国家資格が中小企業診断士
- だからこそ、暗記はもちろん大事だが、それ以上に基礎的な知識の徹底理解をベースにした応用力を問う出題が多い
マークシートだからこそ推測する力が重要

でも、応用力ってそんな簡単につくものなのかな...
でも、すごい能力が必要なわけじゃなくて、問題から出題者の意図を推測する力をみにつければいいだけなんだな。

中小企業診断士の一次試験は、単なる暗記だけでは合格点である60点を獲得することが難しい試験です。
何度もお伝えしている通り、基礎的な知識の徹底理解をベースにした応用力をいかに高めるかがとても重要となります。
応用力を高めるために大切な要素の1つに
- 推測する力
が存在します。
そして、マークシート形式の出題における癖を見抜くポイントさえ知っていれば、問題から出題者の意図を推測する力をカンタンに高めることが可能です。
推測する力を高める4つのポイント
- 断定表現
- あいまい表現
- 因果関係の矛盾
- 常識的・道徳的に考える
断定表現は誤りであることが多い
![断定表現は誤りであることが多い[中小企業診断士アール博士の合格ラボ]](https://kokushi11.com/jsmeca/wp-content/uploads/2020/01/jsmeca-itijisikenn-marksheet-dannteihyougenn-error.png)

100%成功する未来が見えないからこそ、社長から中小企業診断士は必要とされる存在なんだな。

どんなに検討を重ねた最高の一手であっても、必ず成功する保証などありません。
不確定な事象が必ずつきまとうからこそ、成功確率が1%でも高い提案を社長は求めています。
これは、中小企業診断士の資質を見極める一次試験にも当然に当てはめて考える必要があります。
ポイント
- ビジネスの世界で100%の確率で成功することなどない
- だからこそ、社長は中小企業診断士を頼りにしている
- これは中小企業診断士試験でも考え方は同じであるため、絶対や必ずなど断定表現が誤りなことが多い
過去問でチェック
企業経営理論
G.ハメルとC.K.プラハラードによるコア・コンピタンスに関する記述とし て、最も適切なものはどれか。
- コア・コンピタンスは、企業内部で育成していくものであるため、コア・コンピタンスを構成するスキルや技術を使った製品やサービス間で競争が行われるものの、コア・コンピタンスの構成要素であるスキルや技術を獲得するプロセスで企業間の競争が起きることはない。
- コア・コンピタンスは、企業の未来を切り拓くものであり、所有するスキルや技術が現在の製品やサービスの競争力を支えていることに加えて、そのスキルや技術は将来の新製品や新サービスの開発につながるようなものであることが必要である。
- コア・コンピタンスは、顧客が認知する価値を高めるスキルや技術の集合体で あるから、その価値をもたらす個々のスキルや技術を顧客も理解していることが必要である。
- コア・コンピタンスは、他の競争優位の源泉となり得る生産設備や特許権のような会計用語上の「資産」ではないので、貸借対照表上に表れることはなく、コア・コンピタンスの価値が減少することもない。
- コア・コンピタンスは、ユニークな競争能力であり、個々のスキルや技術を束 ねたものであるから、束ねられたスキルや技術を独占的に所有していることに加えて、競合会社の模倣を避けるために個々のスキルや技術も独占的に所有していることが必要である。
参照令和元年度第4問

この問題がもし全くわからなくても、5択から4択にするだけで正答確率が5%もあげられるのはとても大きいんだな。

ポイント
- 企業間競争が起きないことはあり得ないので、断定表現と判断できる
あいまい表現は正解であることが多い
![あいまい表現は正解であることが多い[中小企業診断士アール博士の合格ラボ]](https://kokushi11.com/jsmeca/wp-content/uploads/2020/01/jsmeca-itijisikenn-marksheet-aimai-correctanswer.png)

これらの言葉がでてきた時は要チェックってことなのか...
ビジネスで絶対はないから、1%であっても成功する可能性があることを意味する言葉となっているんだな。

ポイント
- ビジネスの世界で絶対はあり得ない
- どんな戦略や戦術であっても、成功する可能性は限りなく低くいが存在する
- その言葉を表しているのがあいまい表現
- 可能性がある、例外もある、〜なこともあるなど、あいまい表現が選択肢にあったら正答なことが多い
過去問でチェック
企業経営理論
経験効果や規模の経済に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 経験効果に基づくコスト優位を享受するためには、競合企業を上回る市場シェアを継続的に獲得することが、有効な手段となり得る。
- 経験効果は、ある一時点での規模の大きさから生じるコスト優位として定義されることから、経験効果が生じる基本的なメカニズムは、規模の経済と同じである。
- 生産工程を保有しないサービス業では、経験効果は競争優位の源泉にならない。
- 中小企業では、企業規模が小さいことから、規模の経済に基づく競争優位を求めることはできない。
- 同一企業が複数の事業を展開することから生じる「シナジー効果」は、規模の経 済を構成する中心的な要素の 1 つである。

あと、3と4は明らかに断定表現だから選択肢から外してよさそうなことも分かったぞぉぉ〜
だから、独勉クンの解答が正解なんだな。

因果関係の矛盾を見抜けるかどうか
![因果関係の矛盾を見抜けるかどうか[中小企業診断士アール博士の合格ラボ]](https://kokushi11.com/jsmeca/wp-content/uploads/2020/01/jsmeca-itijisikenn-marksheet-causalrelationship-contradiction.png)

だからこそ、論理的思考力を支える因果関係がしっかり組み立てられているかの理解が一次試験でも問われるんだな。

筋道立てて、物事を考える力である論理的思考力(ロジカルシンキング)は中小企業診断士として、経営コンサルタントとして、一番大切なスキルです。
論理的思考力を試されるメインは二次試験ですが、一次試験の問題でも散見されます。
中小企業診断士の根幹となる科目である企業経営理論からは特に多く出題されることを考えると、出題者側から論理的思考力の大切さをています。
因果関係の矛盾を見極める2つのポイント
- 因果関係の一部が成立しない
- 問われている言葉と問題内容がそもそもあっていない
過去問でチェック
企業経営理論
ドメインの定義、および企業ドメインと事業ドメインの決定に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 事業ドメインに関する企業内の関係者間での合意を「ドメイン・コンセンサス」と呼び、その形式には、トップマネジメントが周年記念の場などで、企業のあり方を簡潔に情報発信する必要がある。
- 多角化している企業では、企業ドメインの決定は、競争戦略として差別化の方針を提供し、日常のオペレーションに直接関連する。
- 多角化せず単一の事業を営む企業では、企業ドメインと事業ドメインは同義であり、全社戦略と競争戦略は一体化して特定できる。
- ドメインの定義における機能定義は、エーベルの3次元の顧客層に相当する顧客ニーズと、それに対して自社の提供するサービス内容で定義する方法である。
- ドメインの定義における物理的定義は、エーベルの3次元の技術ではなく、物理的存在である製品によってドメインを定義する。

ちなみに機能定義は、顧客が求める機能によってドメインを定義することだと覚えておくと試験応用力が高まるんだな。

メモ
- 因果関係の矛盾を見抜くには、基礎知識を理解できているかが焦点となる
- ただ、過去問で問われた因果関係のポイントさえ理解しておけば、得点はカンタンにとれる
一般的、常識的に考えることで選択肢を絞れる
![一般的、常識的に考えることで選択肢を絞れる[中小企業診断士アール博士の合格ラボ]](https://kokushi11.com/jsmeca/wp-content/uploads/2020/01/jsmeca-itijisikenn-marksheet-choice.png)

どうしても分からない時や迷った時に、常識的に考えてどうなのかであてはめて考えると、選択肢を絞ることができるんだな。

中小企業診断士の試験に限らず、マークシート形式の問題全般に共通しますが、一般的・常識的に考えられると、選択肢を絞ることができるように問題が設計されています。
それは、常識的・道徳的というフィルターを通して考えことが推測する力を高める要素となっているからです。
一次試験のマークシート対策だけでなく、一般的・常識的に大多数の考えやニーズを捉え、筋の通った経営戦略を策定する上でも重要です。
ポイント
- 一般的・常識的に考えることは推測する力を構成する重要な要素
- 二次試験でも論理的な記述をする際にも一般的・常識的に考えられることは重要な力
過去問でチェック
企業経営理論
G.ハメルとC.K.プラハラードによるコア・コンピタンスに関する記述とし て、最も適切なものはどれか。
- コア・コンピタンスは、企業内部で育成していくものであるため、コア・コンピタンスを構成するスキルや技術を使った製品やサービス間で競争が行われるものの、コア・コンピタンスの構成要素であるスキルや技術を獲得するプロセスで企業間の競争が起きることはない。
- コア・コンピタンスは、企業の未来を切り拓くものであり、所有するスキルや技術が現在の製品やサービスの競争力を支えていることに加えて、そのスキルや技術は将来の新製品や新サービスの開発につながるようなものであることが必要である。
- コア・コンピタンスは、顧客が認知する価値を高めるスキルや技術の集合体で あるから、その価値をもたらす個々のスキルや技術を顧客も理解していることが必要である。
- コア・コンピタンスは、他の競争優位の源泉となり得る生産設備や特許権のような会計用語上の「資産」ではないので、貸借対照表上に表れることはなく、コア・コンピタンスの価値が減少することもない。
- コア・コンピタンスは、ユニークな競争能力であり、個々のスキルや技術を束 ねたものであるから、束ねられたスキルや技術を独占的に所有していることに加えて、競合会社の模倣を避けるために個々のスキルや技術も独占的に所有していることが必要である。
参照令和元年度第4問

どの選択肢が該当するんだろう...
一般的に価値とは、相対的や他と比較して優れいているか劣っているかを判断する言葉として使われることを考えると、価値が減少しないというのは明らかにおかしいと考えらえるんだな。

ポイント
- 価値が安定的と言われる金(ゴールド)でさえ、上げ下げあることをイメージできれば、価値が減少しないものなどないと常識的に考えられる
番外編:迷ったらウの選択肢を選ぶべし
![番外編:迷ったらウの選択肢を選ぶべし[中小企業診断士アール博士の合格ラボ]](https://kokushi11.com/jsmeca/wp-content/uploads/2020/01/jsmeca-itijisikenn-marksheet-uchoice.png)

あとテクニック的な話になるけど、全く分からない問題に遭遇したらウを選択するのもありなんだな。

行動経済学の極端の回避性(松竹梅の法則)と呼ばれる理論であり、人間の本能として、無意識のうちに真ん中を選択する習性を持っています。
例:不動産会社では顧客への決断を迫る営業テクニックの常套手段として極端の回避性(松竹梅の法則)が使われています。
- 新しい暮らしのイメージを想像させるためあえて高価な物件を紹介
- 安価な物件の案内によって新たな暮らしのイメージを損ないたくない気持ちを芽生えさせる
- 両者の真ん中の価格帯の物件を紹介することで、折り合いをつけてもらいやすくなる
どれだけ理性を保っていたとしても習性に抗うことはできないため、中小企業診断士の一次試験にも上手く活用しましょう。
手も足もでない問題に対して、運だけで勝負するのか行動経済学の理論である極端の回避性を武器に選択肢を選ぶのかでは、期待度もかわってきます。
ポイント
- あくまで手も足もでなかった時のお守りとして使うべき
- 4択ならウ、5択ならウかエが極端の回避性にあてはまる
まとめ
![まとめ[中小企業診断士アール博士の合格ラボ]](https://kokushi11.com/jsmeca/wp-content/uploads/2019/11/matome2.jpeg)
中小企業診断士の一次試験を突破するために必要なのは、基礎知識の徹底理解と基礎知識を応用するための推測する(選択肢を絞る)力の2つだけです。
そして、後者の推測する(選択肢を絞る)力を養いたいなら
- 断定表現
- あいまい表現
- 因果関係の矛盾
- 常識的・道徳的に考える
の4つのコツを意識して過去問学習を実践する以外にありません。
過去問学習をする際には意識して取り組み、実力をメキメキとつけることが最短合格への道につながります。

あと暗記はもちろん、基礎知識の徹底理解に軸をいて勉強していくぞぉぉ〜。